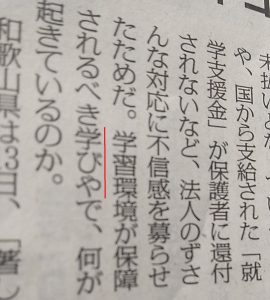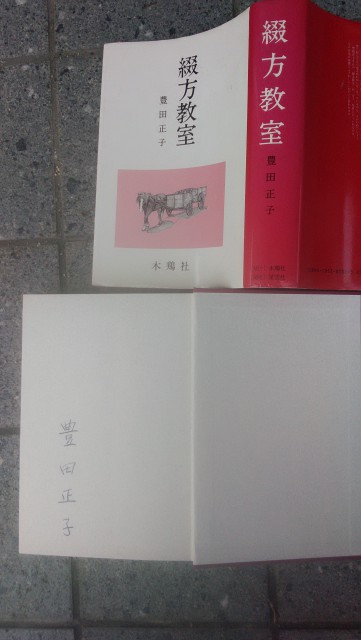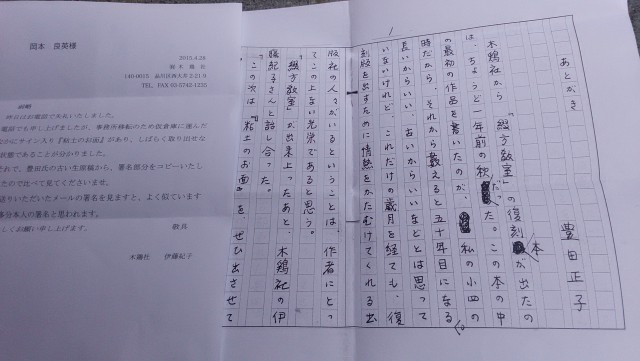今年も例年の如く事後承諾のような状態で「梅雨入り」をしましたが、これだけ気象学が進歩しても梅雨と謂うのは何時まで経っても得体の知れぬものです。梅雨の庭ではいろんな花が咲いていますが、やはり梅雨の時期に似合う花は紫陽花がナンバーワンです。うちの紫陽花は小さいけどとても清潔感に溢れた花を咲かせて居ます^^。
今日は久し振りに漢字の話を聞いてくださいね。良く似た2つの漢字「渉」と「捗」についての当用漢字や常用漢字の変遷を絡めたお話です。前者の訓読みで「渉る(わたる)」音読みで「渉(しょう)」は終戦後設けられた当用漢字で「交渉」などに用いられます。此の字は昭和22年までの旧字体時代には一画少なくて「少」の字の右の点がなかったのに終戦後当用漢字(現在の常用漢字)制定の際に何故か点が付けられて「渉る」に変えられたものです🤬。次に「渉」に良く似た字の「捗」です。ずっと長く準一級の配当漢字でしたが、平成22年に晴れて常用漢字に昇格しました^^。訓読みは「捗る(はかどる)」で音読みは「捗(ちょく)」なんですが、何か怪しい字ですね。「、」がなかったりあったりと現在ではこの二つの漢字が漢字検定2級の受験生達を大いに悩ませて居ます。漢検の2級資格取得は有名文系私立大学が推薦入学の基準にしていることもあって価値がメチャ高く「、」の有る無しの判断はとても重大で「渉」と「捗」では似ていても「、」の有無は月とスッポンくらい違いますが、どうしてこんな紛らわしいことになったのかその理由が今日のお話です。
訓読み「渉る(わたる)」、音読み「渉(ちょく)」の漢字は終戦後当用漢字(現在の常用漢字)制定時に当時の文部省により当用漢字として採用されましたが、それまで「あるく」の「步」と言う字が実は当用漢字に用いられる際に「歩」と右肩の点が付せられることになったため「涉」の字にも同じように「渉」と点が付されたことが原因でした。処が訓読み「捗る(はかどる)」音読み「捗(ちょく)」の方は戦後当用漢字に選ばれず準一級配当漢字として残されたため「、」を付されることがなく、平成22年漸く常用漢字に降格しましたが、戦後75年も経て居り字体が変えられることもなく旧字体の此の字をその儘用いることとなっての「捗」でありました。国語委員会の委員達が昭和22年当時は旧字体の画数の多さに辟易して多くの字が由緒ある画数をバッサリ切っての無惨な文字となったのですが(;;)、省略漢字の代表は警視庁の「庁」(4画)の元が「廳」(25画)であることは余りにも有名であり、国語委員会の杜撰な遣り口が心ある漢字学者から非難されましたが、何せマッカーサーの指揮下にあるGHQの当初の意向が「日本語を全部ローマ字にせよ!」とか「漢字は全部無くせ!」と無法なものでありましたから国民は誰も漢字が残されたことだけに感謝して居たのでした(^0^)/。
閑話休題、捗る(はかどる)の「捗」は上述の第三次改正で漸く常用漢字と成ることが叶いましたが終戦当時とは時代も異なりもうGHQの顔色など窺う必要もない時代でもあって少の右肩の「丶」は旧字体時代からずっと付いて居ない儘の状態で常用漢字になったことが、「渉」との差において漢字検定受験生各位の大いなる混乱を招いたのでした(;;)。私は此の漢字達の絶大な矛盾に対して国語委員会が完全にスルーしていることをとても腹立たしく思っています🤬。
写真はYou tubeに出されている漢字熟語の読み問題の一部でしたが出題の漢字が誤っており、横の「捗」が正しいのに此の字の旁(つくり)は上部が「止」で同じでも下部が「歩」になって居ました。歩の字は戦後作られた当用漢字であり、「歩」の旧字体が「步」で一画少ないのですが、「捗」がずっと常用漢字にされない「準一級の配当漢字」であったためこんなミスが絶えず起こり左の渉が正しいと思い込んで居られる方は居ると思います。You tubeの記載には兎角字の誤りが多く、一言書かせて頂きました。
最後に「涙」を御覧ください。涙って、目から零れるものですから「淚」と「、」を付けてしまいそうですがつけると誤りになります(;;)、実は皆様の直感の方が正しくて昔は「、」の付いた「淚」が正しい字でしたが終戦後の当用漢字改定の際何故か「、」が省かれて「嘘泣きの涙」とされました(;;)。どうして?可怪しいですね🤬真の「なみだ」は現在一級配当漢字の「泪」です!「泪」を用いれば小学生低学年でも容易に理解できるのに国語委員会って全員アホやな!🤬。
「涉と捗」は5月に掲載したものを誤って再び登載してしまったことに気付きました。年は取りたくないもの!ごめんm(_ _)m
先週の読めそうで読めない字 手弱女(たおやめ)。 意味=ほっそりとした気品のある若い女性
今週の読めそうで読めない字 疑うこと(毌れ)